ブレア・ウィッチ・プロジェクト
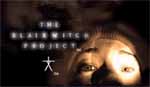
|
|
|
ブレア・ウィッチ・プロジェクト
|
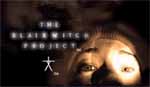 |
| 最低の映画 クリスマス・イヴの日に、最もふさしくない映画をみてやろうと、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』を選択した。クリスマス・イヴの日に、こんな魔女を扱った映画を見ようという不届き者はほとんどいないだろうと、上映開始5分前に映画館に着くと、劇場の空席は5席ほどしかなく、あと三分遅ければ立ち見になるところだった。結局,映画が開始したときには、場内は満員だった。聖なる夜に、こんな魔女映画をみようとは、なんと反キリスト的であろうか。いや、おそらく私と一緒にその日『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』を見た多くの若者は、そんな細かいことは考えていなかったかもしれない。評判になった映画をただカップルで見ようという程度の安易な考えであったか。しかし、その不心得者に対して神は裁きを与えた。もちろん、それは私も含めてである。 1999年も後少しで終わろうとしたこの時期,この聖なる夜、クリスマス・イヴに今年最悪の映画を見ることになろうとは。 『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、最低、最悪の映画である。ひどいとしか言いようがない。確かに劇場予告編、あるいはテレビ・スポットは傑出した出来である。しかし、映画本編のお粗末なこと。 人間の緊張感はせいぜい10分か15分しか続かない。ほとんどの映画製作者は、それを知っているので、手に汗握るシーンが30分以上続くという映画はほとんど存在しない。スリリングなシーンが10分か15分続くと、場面を転回したり、ほっとするようなシーンを入れて観客に休息を与える。それによって、次の緊迫感がより効いてくるのだ。 『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』のテンションは高い。それは映画の冒頭からそうである。ドキュメンタリー・タッチでこれから何が起きるかわからないという雰囲気を盛り上げる。この導入部は観客を引き付ける。しかし、その後も、映像的には同じビデオ映像による主観と、実写フィルム映像が交互につながる。視覚的に飽きてくるし、テンションもずっと同じである。変化というものが全くない。したがって、退屈である。中盤30分をすぎたあたりからは、起きているのもつらいほどに、退屈である。恐怖ではなく、眠気との戦いである。 そして、著しいリアリティの欠如。ドキュメンタリを意識した映像。すなわち、ノンフィクションの世界に観客を迷い込ませるのが,『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』の狙いであったはずだ。にもかかわらず、登場人物たちの行動は実にリアリティがない。はっきりいって、あまりもバカである。バカすぎるが故に全く感情移入が出来ない。 例えば、彼らは二泊目以降、何者かにつけられていることを察知し、恐怖に陥る。しかし、次の日彼らは森の中で、大声で絶叫し、大声で歌を歌い、大声でお互いの名前を呼び合う。これでは、何キロ離れていても、ウィッチたち(?)に彼らの居場所は知れてしまう。そして、彼らの日中の絶叫は、最終日まで延々と続く。彼らは正体不明のウィッチたちを、呼び寄せたくてしかたがなかったようだ。そして、ウィッチたちの気配を感じて、テントから走って逃げ出すが、それも懐中電灯をつけたまま逃げる。なぜ彼らは自分たちの居場所を、そこまでしてウィッチたちに教えなくてはいけないのか。さすがにバカな登場人物たちも、途中でその事実に気づくが、翌日の宿泊ではまた夜間に平気で懐中電灯を使っている。 どうして、わざわざそこまで一生懸命に、ウィッチを呼び寄せるのか。 そして、おまけに命綱とも言える地図を自ら捨ててしまう。恐怖におののいて正常な判断力を失っていた描写と考えられなくもないが、彼らの行動はあまりにも愚かしい。バカな学生の話をリアルに描いているかもしれない。しかし、少なくともリアリティのない登場人物に全く感情移入することはできないし、「こいつらが生きようが死のうがどうでもいい」ような感覚になってくる。むしろ、「こんなバカな奴らは、早く死んで欲しい」とさえ思えてくる。 彼らのバカさ加減は、ラスト・シーンでさらに開花する。行方不明となったジョシュのうめき声を追って、彼らは廃屋に到着する。当然のパーの廃屋であることが疑わしい。いや、パーの廃屋は、焼失したはずだ。しかし、この廃屋に得体の知れないウィッチが、ここにいるかもしれないことは、考え付くだろう。そして、何よりジュシュのうめき声がこの廃屋の中から聞こえているのだろから。この廃屋にジョシュが監禁されて残虐な拷問を受けているだろうことは容易に想像つく。 へザーは「怖い、怖い」と叫んでいたが、一体何を怖がっていたのか。それは、ブレア・ウィッチの存在を否定できなくなったから、間違いなく存在すると思っているからこそ、恐怖を感じたのではないか。にもかかわらず、へザーとマイクは、ジョシュのうめき声がするという理由で、勇敢にも何の武器も持たずに躊躇なく廃屋に入っていく。ブレア・ウィッチがいるかもしれない廃屋に。彼らの行動は滅茶苦茶である。ここで、棒切れか何かを手にして、廃屋に入っていくのなら、ジョシュを助けるという目的なのだろうという理由もつくが、彼ら二人は手ぶらで、いやカメラを回すという十分な理性を備えながら、彼らが最大限に恐怖しているブレアの廃屋に入っていく。もうリアリティのかけらもない。何の防備もしてないわけだから、殺されてあたりまえである。何の意外性も恐怖感もない。そして、映画は終わる。 結局、ブレア・ウィッチに関しては、何も明らかにされない。映像スタイルだけリアルで、人物の行動に全くのリアリティがない。自殺志願者たちの自殺旅行といったところだ。彼らはウィッチに襲撃されなくても、早晩遭難して死んでいただろう。馬鹿らしくて、見ているのもつらいほどであった。 この感想は、どうやら私だけのものではなかった。映画が終わりクレジットに変わった瞬間,「はあ」という呆れた声が聞こえた。そして、「 クスッ」という笑い声も。自業自得としか思えない、ヘザーの行動はもはやお笑いなのである。 エレベーター・ホールでエレベーターを待つ間,カップルたちの感想に聞き耳を立てる。「最悪のクリスマス・イヴだったね」と女性にわびる男。「これなら、ラーメン二杯食べた方が良かった」「途中で退出した人がいたけど、その判断は正しかった」等、惨憺たるものである。 聖なる夜に、魔女の映画を見ようとした不心得物に対して,神は鉄槌を下した。 この架空のドキュメントタリー映画を、事実と錯覚させるために、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』のホーム・ページでは、登場人物たちが実際の人物であるかのような工夫をしている。これは、私に言わせると全くお粗末としか良いようがない。例えば、ヘザーの日記というのが、公開されている。彼女の撮影中の日記である。この日記を読むと、彼女が極めて洞察に深く、幅広い知識を有する頭の良い女性であることがわかるが、それは劇中のヘザーとは別人である。わめくだけのバカ女が、こんな日記を書けるはずがないではないか。あまりにもの解離に、ただあきれるだけである。 魔女のプロパガンダ |
| すなわち、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、魔女賛美映画であり、悪魔主義肯定映画であり、反キリスト映画であるという点である。 その根拠は,無数にあるが,まず映画の最初にその証拠が隠されている。製作プロダクションのロゴ「ARTISAN」が出る。そして、映画の本編が始まるが、「ARTISAN」とは何だろう。「職人」という意味だが、私には「SATAN(サタン)」のアナグラム(文字の並び替え)にしか思えない。そんなバカなと思うかもしれない。しかし、アーティザン社の近作として『THE NINTH GATE(第九の門)』という作品が控えている。これは、「第九の門」というサタンその人を召還する呪文が書かれた悪魔の書をめぐる物語である。まさにアーティザン社が配給するにふさわしい作品ではないか。 「ARTISAN」社は配給会社である。『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、アメリカの無名フィルムメーカー、ダニエル・ミリックとエドゥアルド・サンチェスがサンダンス映画祭に出品した制作費わずか約600万円の映画であった。そのマイナー映画をインディーズ系の配給会社アーティザン社が買い付け、興行収入1億ドルを突破する作品となったのである。 |
|
| 今後のアーティザン社の配給作品を見ていけば、アーティザン社が悪魔主義に対して肯定的であることは、証明されるであろう。 『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』で貫徹されるリアリズム。そのリアリズムは、何を訴えていたか。それは、現代のアメリカに魔女が実在するという事実である。現代のアメリカで魔女崇拝、悪魔主義が信奉されており、決して小さくない勢力を築いていると思われる。信じたくなければ信じる必要はないが、実際ハリウッドは、アントン・ラヴィら本物の悪魔主義者と結託して悪魔主義肯定映画を作りつづけてきた経緯がある。 実際、映画の宣伝力のおかげもあり、悪魔主義は、アメリカの底辺にしっかりと広がりつつあるようだ。実際、この『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』が、これほどの大ヒットが記録されているのも、アメリカ社会に敬虔なクリスチャンが減っている(特に若者たちの間で)ことと関係していると推測する。 アメリカにおけるキリスト教ばなれと、犯罪や社会の荒廃とは決して無関係ではないだろう。アメリカが理性と正義と秩序が保たれた国家であり続けて欲しい。そのためには、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』のような悪魔主義肯定映画は、その存在自体を認めるわけにはいかない。 『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』が、日本でヒットしないことを心から願いたい。 |
| ナインス・ゲート | 公式ホーム・ページ |
| 遅まきながら、『ナインス・ゲート』をビデオで見た。 あのロマン・ポランスキーの監督作品である。「あの」というのは、『ローズマリーの赤ちゃん』(68年)の監督であるという意味。そして、その妻、シャロン・テートが惨殺されたという二つの意味を担っている。 ポランスキーは一体何をしていたのか。この『ナインス・ゲート』は、『ローズマリーの赤ちゃん』以来三一ねんぶりのオカルト映画ということになる。『ナインス・ゲート』は、悪魔の力をかりて、「第九の扉」を開くという話だが、「第九の扉」の封印と一緒に、ポランスキーのオカルト映画への封印が解かれた。 |
 |
| 全編を貫かれる、張り詰めた雰囲気。緊迫感。サスペンスとして、よくできた映画だ。しかし、興味はおのずと、そのテーマへと向かってしまう。ポランスキーが悪魔をどう描いているのか。 ポランスキーという人間は、どうやら悪魔に魅入られている。悪魔の書の鑑定を依頼するバルカン。そして、ジョニー・ディップ演じる古書鑑定人コルソ。バルカンやコルソ同様に、ポランスキーもまた悪魔に魅入られている。 ポランスキーは悪魔肯定映画、『ローズマリーの赤ちゃん』を監督し、世界に衝撃を与えた。そしてその後、愛妻シャロン・テートを、チャールズ・マンソンとそのファミリーに惨殺される。しかし、そうした悲劇的な事件は、彼の悪魔に対する考えに全く影響をおよぼさなかったのだろう。それが、『ナインス・ゲート』には、強く現れている。 |
| 『ナインス・ゲート』は、『ローズマリーの赤ちゃん』の今日的な焼き直しとも見える。『ローズマリーの赤ちゃん』ほど直接的に悪魔の存在を描いてはいない。しかし、悪魔の手を借りて万能の力を手に入れようという、悪魔に魅入られた人々が描かれる。 悪魔は存在するのか。『ナインス・ゲート』のラストは、はっきりとした結論を出さない。しかし、悪魔に魅入られた人々は存在する。彼らは悪魔に魂を売り渡したかのように、人を殺すことに全くの罪悪感も持たない。悪魔は、明らかに人々に精神的な影響を与えつづけている。そうした意味で、悪魔は存在するのだ。やはり、『ナインス・ゲート』もまた、『ローズマリーの赤ちゃん』と同様に、悪魔肯定のスタンスで描かれている。 『ローズマリーの赤ちゃん』では、ラストで悪魔の子を産んだローズマリーが、自らの子供と対面する。拒絶。しかしその後、彼女は自らのこどもを受容する。悪魔の排除ではなく、悪魔の受容によって映画は幕を閉じる。 悪魔の力を得る儀式を行うバルカン。その儀式に直面するコルソ。コルソはその儀式を見て、それを阻止するのではなく、それを横取りして、自らが悪魔の力を得ようとするのである。悪魔に対して半信半疑で調査を進めていくコルソが、悪魔の書を調べていくうちに、悪魔に感化され、悪魔の道にはまっていく。『ナインス・ゲート』もまた、悪魔を受容する映画として作られているのである。 |
|
| 『ナインス・ゲート』は、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』と同様に、「ARTISAN」の配給である。『ナインス・ゲート』は、フランス・スペインの合作映画であり、アメリカ映画ではない。ヨーロッパ映画である『ナインス・ゲート』を「ARTISAN」が買い付けてきて、アメリカで公開したのである。 「ARTISAN」に「SATAN」の文字が含まれること、そして悪魔肯定のプロパガンダを持って、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』が公開されたという、私の仮説は『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』のコーナーで既に紹介した。しかし、その仮説はやはり、正しいとしか思えない。『ナインス・ゲート』を見てそれを確信した。 『ナインス・ゲート』にも、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』と同様に、魔女が登場する。その一人が、リアナことサンマルタン婦人である。彼女は、コルソの先回りをして、悪魔の書の版画を奪っていく。もちろん、悪魔の力を得る儀式を行うためである。「銀の蛇」と呼ばれる秘密結社は、魔術的な儀式を行う魔女集団として描かれる。彼女の名前は、「リアナ・ド・サンマルタン」、劇中の看板では「サンマルタン」はフランス語で、「St MALTIN」と書かれているが、英語風にスペルアウトすれば「SANMALTAN」、最初と最後の文字をつなげて読めば「SATAN」(サタン)である。リアナ・ド・サンマルタンは魔女であるが、これは悪魔崇拝者という意味での魔女にすぎない。 一方、ことあるごとにコルソを助ける謎の女性。空中を飛び、屈強な男性をも殴り倒す圧倒的な力。彼女の正体は、何なのか。最後まで彼女の正体は不明であるが、彼女の正体は何であったか。 まず、彼女の登場シーンを見てみよう。それは、バルカンが魔女についての講義をしている講堂に、彼女はいた。バルカンが魔女の話をしていたのは、偶然か。いや、偶然ではあるまい。彼の専門は悪魔である。魔女の話ではなく、悪魔の話をしている方が普通だろう。 パリに向かう飛行機の途中で、コルソは彼女に聞く。「君は守護天使(guardian angel)か?」彼女は答える。「まあ、そんなものね。」 しかし、彼女は天使ではないだろう。コルソが、「ナインス・ゲート」の謎を解き、そして第9の扉を開かせることに、全力を尽くすのである。 少なくとも彼女は、人間ではなさそうである。それは、彼女が空中を飛んで降りてくるシーンが(右写真)がそれを示す。 写真Aと写真Bを見比べて欲しい。「ナインス・ゲート」の9枚目の版画に出てくる女性と、コルソを助ける謎の女性の顔がそっくりである。おまけに、写真Aのシーンでは版画と同様に、手に本を持っている。 この版画の女性は、何者か。少なくとも、悪魔そのものではなさそうだ。ナイス・ゲートに導く悪魔の使いといったところだろう。 謎の女性も同様に理解できる。彼女が悪魔そのものであるとするには、彼女に悪魔的な側面が少なすぎる。コルソに「ナインス・ゲート」を開かせるという命令を悪魔から受けた、悪魔の手先と理解される。 彼女の登場シーンと合わせて、魔女といっても良いかもしれない。 『ナインス・ゲート』は『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』と同様に、現代に魔女が存在するということを描いている映画なのである。これが、偶然と言えるのか。言えるはずがない。配給会社「ARTISAN」は、一本はアメリカのインディーズ映画『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』、そしてもう一本はフランス・スペインの合作映画という、全く関係のないに作品を買い付けた。そこに共通するのは、唯一悪魔肯定、魔女肯定というテーマだけなのである。 |
|
| 『ナインス・ゲート』のラスト。第九の扉が開くシーンがあまりにもあっさりとしすぎている、そうした批判もあるだろう。映画のタイトル、そして劇中で登場する悪魔の書も「第九の扉」であるから、第九の扉に対する感心が高まっていくのもわかる。しかし、この映画の作り手の興味は、第九の扉が開かれた先にはないのである。むしろ、その前。既に書いたように、現代の魔女、悪魔主義者の存在を描くことが主眼と考えるなら、このあっさりとしたラストにも納得がいくというものである。 魔女が存在するというプロパガンダをすることにいかほどの意味があるのか。それは私にはわからないが、今後の「ARTISAN」の動向には注意を払った方が良いだろう。 |
|
|
| [映画の精神医学 HOME][映画ブログ][激辛カレー批評] [精神医学・心理学本の全て][必ず役に立つ無料レポート] [毎日50人 奇跡のメルマガ読者獲得法] |