読者の「インランド・エンパイア」解読 第1弾
「インランド・エンパイア」は、「一言で言うと、どんな話だったの?」
カロリーナ・グルシカ:ロスト・ガールの葛藤の話だと思います。
ロコモーション・ギャルズは全て自分(ロスト・ガール)の分身。
映画の前半、近所に越してきたと言うおばさんの
「行動には結果が伴う」の様な台詞。
様々な状況で自分がとりえる行動の1つ1つの象徴が
ロコモーション・ギャルズ1人1人であり、その中には破滅的な未来への
行動だけでなく、より良く生きる為の可能性をも含んでいると思う。
そして、各状況下でどの行動(ギャル)を選択するかを決めているのが
「ウサギ人間」。
人格の支配者と言うか、管理者と言うか、調整者。
より良く生きたいと願う人間と納得し辛い現実とのギャップを
生み出す象徴のような存在。
このウサギ人間は別のシーンでは、メガネの男性でも有り、
別の男性でもあり...
そもそもタイトルの「インランド」とはこのウサギ人間に象徴される
人間の内面を意味してるのでは?
ロスト・ガールが自分の内面(自分自身)に訴え掛ける時にウサギ人間
宛に電話が鳴るのでしょう。
そして、テレビの中のウサギの行動により起こる笑いは冷たい第三者を
表しているのでは?
映画は一見バラバラな様に見えましたが、1人の人間の様々な葛藤の
繰り返しとして見ると繋がってくる様に思えました。
エンディング近くからは、ロスト・ガールの葛藤の結果、
新しい世界が開けた様に感じます。
なにか一つ乗り越えたような...
(状況からはニッキーさえもロスト・ガールの分身であったと思います。)
【樺沢コメント】
この解読は、私が考えていた「インランド・エンパイア」の全体像とはかなり異なるものではありましたが、言われてみると「そういう見方もあり得るのか・・・」と、リンチ作品の多面性に驚かされた次第です。
●「一言で言うと、どんな話だったの?」
ロスト・ガールの精神性回復プロセスの映画。
自分はTVの砂嵐画面の中に映像を見て取っているロスト・ガールをみて
そう感じました。
この映画で描かれる事柄のうち、ロスト・ガールの部分と、映画
「47」の部分は事実だと思います。
ニッキー・グレースはロスト・ガールの「内なる帝国」内の彼女自身の
投影。
でも「内なる帝国」の中の登場人物たちは自分たちが妄想上の人物だと
の自覚がないため辻褄が合わなくなっているのでは?
●「ウサギ人間って何?」
ロスト・ガールとインランド・エンパイアを繋ぐ入り口。
ロスト・ハイウェイのホワイトロッジみたいな存在。
それがロスト・ガールの意識内にある。
●「ロコモーション・ギャルズって何者?」
ニッキーの自分自身の存在の不安定感(妄想における産物なの
で。。。)が彼女に見せるインランド・エンパイア内の現実
と妄想部分の架け橋の象徴?
●「なんでポーランドが出てくるのか?」
というよりは、ポーランド内での話。
ハリウッド自体が虚構。
妄想、虚構と書きましたが、どこかの世界では現実なのでは?
インランド・エンパイア内の人物がロスト・ガールの操り人形ではなく
意思を持っているように、この現実と言われる世界もそんな風に成り
立っているのではないか? と。
とりあえずもう一度見たい映画です。
【樺沢コメント】
素晴らしい解読ありがとうございます。
ここまで分かれば、私がわざわざ解読する必要もない気がしてきます。
「インランド・エンパイア」は、大きく分ければ二通りの見方ができると思います。
一つは、ハリウッド女優ニッキーを中心にすえて見る見方。
もう一つは、ロスト・ガールを中心に据えてみる見方。
前者の話だと、「トラブルに見舞われた女性」の話となります。
後者の話だと、「一人の女性の癒しの物語」となります。
表が「悲劇」で、その裏が「救いの物語」になっている。
どちらを「表」と見るかは観客にゆだねられていますが、見方によって
「悲劇」にも見えるし、「救済の物語」にも見える。
そういえば、「マルホランド・ドライブ」も、全く同じ構造を持っていますね。
リンチ暴走。
マルホランドで成功したもんだからもう誰も止められない、
って感じの暴走また暴走。
おーい、どこまで行くんだ。そろそろ戻ってこい。
やっと戻ったと思うと裏切られてさらに複雑に入れ子構造になっていく。
わかんない系の映画(という括りもひどいですが)としては
ゴダールもフェリーニもブニュエルもあったし、黒澤の「夢」だって
こんな夢なんだから説明などいらない、って言われれば誰も何も言えないのだ
けれど、
どうもデビットリンチの映画は「じゃあ勝手に好きなように撮れば。」
と割り切れない、なんとか解釈したくなるところがあって、
よくも悪くもアメリカ映画なんですよね。
マルホランドの延長にある事は前回の監督役が役者だったり
また劇場がキーになっていたり
またセリフの読み合わせがあったりすることで容易に想像がつくけれど
前作が基本的に前半と後半で出来ていたのに比べて
女優の今、劇中劇、ポーランド女性の今(今ではないのかも)、ポーランド
の劇中劇
の最低4つのワールドがあって、さらにそれぞれに現実と幻想があるみたいな。
あとウサギの部屋ですね。
これだけ入り組んで、監督自身思いつきで脈絡なく撮りまくったと言ってい
るのだから
見てる方が翻弄されるのは当たり前です。
ウサギはTVシリーズでコケた「RABBITS」というののシーン応用で
ナオミワッツとローラハリングがかぶりものしてたって?!
パンフ買ってわかったことが沢山ありますね。
で、ちょっとした考察としては、このウサギのシーンは全体の縮図ではないだ
ろうか、
ってことです。
舞台劇のようだけれど視点はずっと高いところ(観客席の上の方)にあって、
ちょうどマルホランドのシレンシオ劇場と同じくらいの視点で、
この映画の中で行われている事はすべて(一見現実のようでも)劇中劇なんで
すよ。
役者も監督も作品もそうやって見下ろされて、笑われたりしているんですよ。
だからローラダーンもドアを開けたらそこは誰もいない空虚な舞台なんですよ。
ということがテーマなんじゃなかろうか。
つまりまた今回も虚構と思ったら現実?と思ったらまた虚構?
という映像遊びを3時間もかけてやってしまったということですか。
路地裏のドアを開けると数日前のセットの裏側につながっている。
劇場の裏口を抜けるとまた暗い階段の部屋に戻ってしまう。
ドライバーが刺さっていたはずの女が実は刺す側に変わっている。
など、解釈というよりは時間や起きた事の整合性を無視した暴走。
これはもう楽しむしかないでしょう。
お、そうきましたか。 じゃこう来るかな? え! そっちじゃない、
じゃあれはどうなるの、
と伏線から伏線へ引き回されてよくわからないうちに大団円(座頭市を思い出
しましたが)
でとりあえず見終わった感だけは与えてくれる。
リンチって意外にいい人じゃん。
パンフにもありましたが2001年的シーン(ベッドルームから顔のアップ
へ行き、視線を利用して場面転換、
というのを多様したところかな?)もあったし、さらにシャイニングも意識し
てるのではないだろうか?(妙なシンメトリー構図とか、廊下の47号室を
発見するシーンとか、そもそもウサギ男を見た瞬間にシャイニングを
思い出した。)
音の作り方もキューブリック的ですよね。
最後にTVを見ている女性と同化するところは、すべては彼女(ポーランド
女)の幻想でした、
と解釈している人もいるようですがそれだとちょっとつまらない。
泣きながらTVを見る女性はウサギ達をも客観視しているのだから明らかにこ
ちら側の(観客側の)人間として存在しています。
ローラダーンがCUTのあとさまよって、劇場で自分の出ているシーンを見る
のは、彼女がこちら側、つまり見る側にまわったというよりも、
すべての行動は見られていることを実感するシーンだったと思います。
47の部屋を開けてから執拗にスポットライトの逆光が入るのも
つまり見られている事の象徴。
あるいは映画を見ている観客にさえ、お前達は見られている、
という感覚を味合わせたくて意図的に入れたシーンかも知れません。
ものすごく要約すると
女優が現実と役の中の自分との区別がつかなくなって、過去の作品47の
女性とも同化して、彼女の視点にまでなってしまうけれど、それも
すべては虚構。
みたいなことでしょうか。
あとはDVDが出たらマルホの時のようにメモを取りながら
気になる点を確認して楽しみます。
またベアトリーチェの肖像らしき物が壁にあったような気もしますし、、
(投稿者 玄さん)
カロリーナ・グルシカ:ロスト・ガールの葛藤の話だと思います。
ロコモーション・ギャルズは全て自分(ロスト・ガール)の分身。
映画の前半、近所に越してきたと言うおばさんの
「行動には結果が伴う」の様な台詞。
様々な状況で自分がとりえる行動の1つ1つの象徴が
ロコモーション・ギャルズ1人1人であり、その中には破滅的な未来への
行動だけでなく、より良く生きる為の可能性をも含んでいると思う。
そして、各状況下でどの行動(ギャル)を選択するかを決めているのが
「ウサギ人間」。
人格の支配者と言うか、管理者と言うか、調整者。
より良く生きたいと願う人間と納得し辛い現実とのギャップを
生み出す象徴のような存在。
このウサギ人間は別のシーンでは、メガネの男性でも有り、
別の男性でもあり...
そもそもタイトルの「インランド」とはこのウサギ人間に象徴される
人間の内面を意味してるのでは?
ロスト・ガールが自分の内面(自分自身)に訴え掛ける時にウサギ人間
宛に電話が鳴るのでしょう。
そして、テレビの中のウサギの行動により起こる笑いは冷たい第三者を
表しているのでは?
映画は一見バラバラな様に見えましたが、1人の人間の様々な葛藤の
繰り返しとして見ると繋がってくる様に思えました。
エンディング近くからは、ロスト・ガールの葛藤の結果、
新しい世界が開けた様に感じます。
なにか一つ乗り越えたような...
(状況からはニッキーさえもロスト・ガールの分身であったと思います。)
【樺沢コメント】
この解読は、私が考えていた「インランド・エンパイア」の全体像とはかなり異なるものではありましたが、言われてみると「そういう見方もあり得るのか・・・」と、リンチ作品の多面性に驚かされた次第です。
読者の「インランド・エンパイア」解読 第2弾
●「一言で言うと、どんな話だったの?」
ロスト・ガールの精神性回復プロセスの映画。
自分はTVの砂嵐画面の中に映像を見て取っているロスト・ガールをみて
そう感じました。
この映画で描かれる事柄のうち、ロスト・ガールの部分と、映画
「47」の部分は事実だと思います。
ニッキー・グレースはロスト・ガールの「内なる帝国」内の彼女自身の
投影。
でも「内なる帝国」の中の登場人物たちは自分たちが妄想上の人物だと
の自覚がないため辻褄が合わなくなっているのでは?
●「ウサギ人間って何?」
ロスト・ガールとインランド・エンパイアを繋ぐ入り口。
ロスト・ハイウェイのホワイトロッジみたいな存在。
それがロスト・ガールの意識内にある。
●「ロコモーション・ギャルズって何者?」
ニッキーの自分自身の存在の不安定感(妄想における産物なの
で。。。)が彼女に見せるインランド・エンパイア内の現実
と妄想部分の架け橋の象徴?
●「なんでポーランドが出てくるのか?」
というよりは、ポーランド内での話。
ハリウッド自体が虚構。
妄想、虚構と書きましたが、どこかの世界では現実なのでは?
インランド・エンパイア内の人物がロスト・ガールの操り人形ではなく
意思を持っているように、この現実と言われる世界もそんな風に成り
立っているのではないか? と。
とりあえずもう一度見たい映画です。
【樺沢コメント】
素晴らしい解読ありがとうございます。
ここまで分かれば、私がわざわざ解読する必要もない気がしてきます。
「インランド・エンパイア」は、大きく分ければ二通りの見方ができると思います。
一つは、ハリウッド女優ニッキーを中心にすえて見る見方。
もう一つは、ロスト・ガールを中心に据えてみる見方。
前者の話だと、「トラブルに見舞われた女性」の話となります。
後者の話だと、「一人の女性の癒しの物語」となります。
表が「悲劇」で、その裏が「救いの物語」になっている。
どちらを「表」と見るかは観客にゆだねられていますが、見方によって
「悲劇」にも見えるし、「救済の物語」にも見える。
そういえば、「マルホランド・ドライブ」も、全く同じ構造を持っていますね。
読者の「インランド・エンパイア」解読 第3弾
リンチ暴走。
マルホランドで成功したもんだからもう誰も止められない、
って感じの暴走また暴走。
おーい、どこまで行くんだ。そろそろ戻ってこい。
やっと戻ったと思うと裏切られてさらに複雑に入れ子構造になっていく。
わかんない系の映画(という括りもひどいですが)としては
ゴダールもフェリーニもブニュエルもあったし、黒澤の「夢」だって
こんな夢なんだから説明などいらない、って言われれば誰も何も言えないのだ
けれど、
どうもデビットリンチの映画は「じゃあ勝手に好きなように撮れば。」
と割り切れない、なんとか解釈したくなるところがあって、
よくも悪くもアメリカ映画なんですよね。
マルホランドの延長にある事は前回の監督役が役者だったり
また劇場がキーになっていたり
またセリフの読み合わせがあったりすることで容易に想像がつくけれど
前作が基本的に前半と後半で出来ていたのに比べて
女優の今、劇中劇、ポーランド女性の今(今ではないのかも)、ポーランド
の劇中劇
の最低4つのワールドがあって、さらにそれぞれに現実と幻想があるみたいな。
あとウサギの部屋ですね。
これだけ入り組んで、監督自身思いつきで脈絡なく撮りまくったと言ってい
るのだから
見てる方が翻弄されるのは当たり前です。
ウサギはTVシリーズでコケた「RABBITS」というののシーン応用で
ナオミワッツとローラハリングがかぶりものしてたって?!
パンフ買ってわかったことが沢山ありますね。
で、ちょっとした考察としては、このウサギのシーンは全体の縮図ではないだ
ろうか、
ってことです。
舞台劇のようだけれど視点はずっと高いところ(観客席の上の方)にあって、
ちょうどマルホランドのシレンシオ劇場と同じくらいの視点で、
この映画の中で行われている事はすべて(一見現実のようでも)劇中劇なんで
すよ。
役者も監督も作品もそうやって見下ろされて、笑われたりしているんですよ。
だからローラダーンもドアを開けたらそこは誰もいない空虚な舞台なんですよ。
ということがテーマなんじゃなかろうか。
つまりまた今回も虚構と思ったら現実?と思ったらまた虚構?
という映像遊びを3時間もかけてやってしまったということですか。
路地裏のドアを開けると数日前のセットの裏側につながっている。
劇場の裏口を抜けるとまた暗い階段の部屋に戻ってしまう。
ドライバーが刺さっていたはずの女が実は刺す側に変わっている。
など、解釈というよりは時間や起きた事の整合性を無視した暴走。
これはもう楽しむしかないでしょう。
お、そうきましたか。 じゃこう来るかな? え! そっちじゃない、
じゃあれはどうなるの、
と伏線から伏線へ引き回されてよくわからないうちに大団円(座頭市を思い出
しましたが)
でとりあえず見終わった感だけは与えてくれる。
リンチって意外にいい人じゃん。
パンフにもありましたが2001年的シーン(ベッドルームから顔のアップ
へ行き、視線を利用して場面転換、
というのを多様したところかな?)もあったし、さらにシャイニングも意識し
てるのではないだろうか?(妙なシンメトリー構図とか、廊下の47号室を
発見するシーンとか、そもそもウサギ男を見た瞬間にシャイニングを
思い出した。)
音の作り方もキューブリック的ですよね。
最後にTVを見ている女性と同化するところは、すべては彼女(ポーランド
女)の幻想でした、
と解釈している人もいるようですがそれだとちょっとつまらない。
泣きながらTVを見る女性はウサギ達をも客観視しているのだから明らかにこ
ちら側の(観客側の)人間として存在しています。
ローラダーンがCUTのあとさまよって、劇場で自分の出ているシーンを見る
のは、彼女がこちら側、つまり見る側にまわったというよりも、
すべての行動は見られていることを実感するシーンだったと思います。
47の部屋を開けてから執拗にスポットライトの逆光が入るのも
つまり見られている事の象徴。
あるいは映画を見ている観客にさえ、お前達は見られている、
という感覚を味合わせたくて意図的に入れたシーンかも知れません。
ものすごく要約すると
女優が現実と役の中の自分との区別がつかなくなって、過去の作品47の
女性とも同化して、彼女の視点にまでなってしまうけれど、それも
すべては虚構。
みたいなことでしょうか。
あとはDVDが出たらマルホの時のようにメモを取りながら
気になる点を確認して楽しみます。
またベアトリーチェの肖像らしき物が壁にあったような気もしますし、、
(投稿者 玄さん)
無料レポート「インランド・エンパイアの解読」
- 精神科医樺沢紫苑が、「難解」と言われるディヴィッド・リンチ監督の
「インランド・エンパイア」を解読しました。 - ウサギ人間って何? ロコモーション・ガールズって何?
- どこまでが夢で、どこまでが現実? どこまで正気でどこから狂気?
- これを読めば、あなたの「インランド・エンパイア」の謎は、
全てスッキリと解決します。 - 今すぐ、無料レポートを、ダウンロードしてください。
-
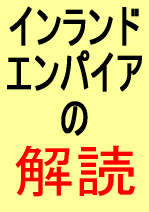
-
- Yahoo! メール、携帯のメールアドレスには、返信が届きません。
・ご記入いただきましたアドレスに、ダウンロードURLを送信します。
- (注意事項)
この無料レポートをダウンロードされた場合、佐々木信幸によって
メールマガジン「シカゴ発 映画の精神医学」(0000136378)
メールマガジン「ビジネス心理学」(0000173155)に代理登録されます。
メールマガジンは「まぐまぐ!」のシステムを利用して配信されています。
登録されたメールマガジンは以下のページから解除することができます。
http://www.mag2.com/m/0000136378.html
http://www.mag2.com/m/0000173155.html
※なお、「まぐまぐ!」が発行している公式メールマガジンには
登録されません。